日常に溶け込む1400年の歴史と祈り~浅草寺が紡ぐ今と昔の物語~

東京都台東区・浅草。下町の風情を色濃く残すこの地に、約1400年の歴史を誇る観音霊場「浅草寺」があります。観音霊場とは、観音様の慈悲と智慧によって、あらゆる人々を救済へと導く寺院のこと。浅草寺は、寺院そのものの魅力もさることながら、総門に鎮座する「雷門」の赤提灯に風神雷神像など、思わず写真に収めたくなるフォトスポットが盛りだくさん。街並みからグルメに至るまで「和」の要素が溢れ、国内外から年間3000万人が訪れる日本を代表する観光地です。今回は、そんな日本最古の寺院・浅草寺の歴史と文化、そして現代に息づく魅力をご紹介します。
浅草寺、はじまりの物語
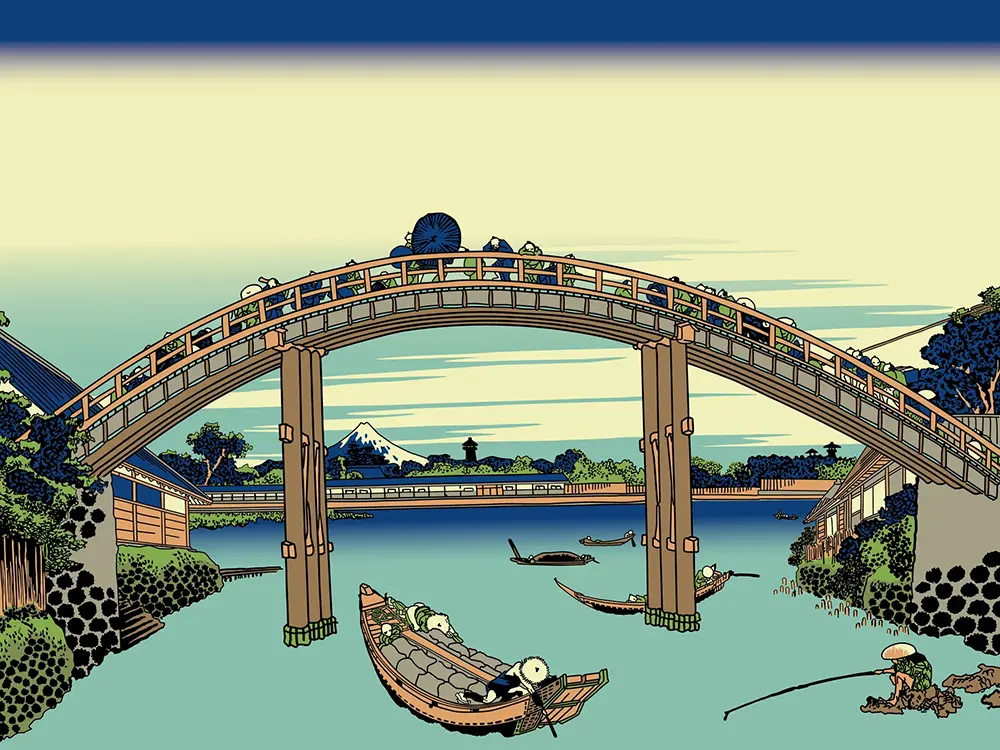
浅草寺の創設は、寺伝によると約1400年前、飛鳥時代の628年(推古天皇期)まで遡ります。
檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)の兄弟が、隅田川にて漁をしていた際、聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)像を網で引き上げました。仏像のことをあまり知らなかった兄弟は、その像を川に戻し、場所を変えて何度も漁を試みましたが、網にかかるのは尊像ばかり。結局その日、魚は一匹も捕れず、兄弟はついにその尊像を持ち帰ったといいます。
兄弟は尊像について土地の長であった土師中知(はじのなかとも)に相談しました。像を見た中知は、これが聖観世音菩薩の尊像であると悟り、自ら出家して自宅を寺へと改装し、観音像をお堂に祀りました。以後、彼は生涯を観音信仰と礼拝供養に捧げ、これが浅草寺の起こりとされています。
その後、645年には僧・勝海上人(しょうかいしょうにん)が観音堂を建立し、本尊は秘仏として祀られるようになります。また、857年には慈覚大師・円仁(じかくだいしえんにん)による中興が行われ、浅草寺は関東における観音信仰の中心地としての基盤を固めていきました。
平安期から鎌倉・室町期を経て、武将や幕府からも庇護を受け、やがて江戸時代には徳川家康によって祈願所と定められた浅草寺。江戸の庶民にとっても観音様は心の拠りどころであり、門前町や仲見世の発展とともに、この浅草寺は信仰と文化の両面で大きな役割を担う存在となっていきました。
平安時代後期には地震や火災での堂宇損壊、数百年を経て、1945年の東京大空襲での本堂焼失など、浅草寺は幾多の試練に見舞われてきました。しかしその度に修繕され、信仰心とともに現代へと受け継がれています。
武将たちが託した、勝利と勇気の祈り

浅草寺は、名だたる武将たちが戦勝祈願のために訪れた寺院としても有名です。
源頼朝は平氏追討の戦勝祈願に参拝し、その後の奥州征討の際にも田園を寄進して加護を願いました。また、頼朝の父・源義朝も観音像を奉納し、戦勝祈願を行ったと伝えられています。奉納された観音像「木造観音菩薩立像(別名:榎本尊・えのきほんぞん)」は、現在も正月の「温座秘法陀羅尼会(おんざひほうだらにえ)」で本尊として祀られています。
さらに、徳川家康も大切な決戦前に浅草寺で祈願を行いました。天下分け目の戦い「関ヶ原の戦い」の戦勝祈願に訪れ、その祈願の甲斐あってか見事に勝利を収めたのです。
浅草寺のシンボル〜雷門と赤提灯〜

今も昔も、訪れる人々の心を掴んで離さない浅草寺。その魅力は、信仰や歴史の重みだけにとどまりません。
浅草寺の総門に堂々と鎮座する大きな赤提灯。大きく書かれた「雷門」の文字が目を引き、多くの人が足を止めて思わず写真を撮ってしまう、唯一無二の存在感を放っています。
高さ3.9m、直径3.3m、なんと重さ700kgにもなる赤提灯は、底部に龍の彫刻が施され、正門の威厳をより一層際立たせています。実はこの赤提灯、京都の職人の手によって作られており、一定の年数ごとに新しいものに取り替えられています。そのあまりの大きさにより高速道路は使用できず、一般道を二泊三日もかけて、京都から遠路はるばる、大切に運ばれてくるのだそう。
その赤提灯の両サイドを守るように立つのは、風神雷神像の勇ましい姿。「雷門」の正式名称「風雷神門」は、この二体の像に由来しており、風雨順次と五穀豊穣の祈りが込められています。
雷門だけじゃない!浅草寺の魅力
浅草寺といえば雷門のイメージが強いですが、見どころはそれだけではありません。広い境内には大本堂のほかに複数のお堂や五重塔など訪れるべきスポットが盛りだくさん。これだけ多くの観光客に親しまれていますが、西側に国の名勝に指定された庭園が広がっていることを知る人は、意外と少ないかもしれません。
浅草寺を訪れた際には、ぜひゆっくりと時間を使い、その広い境内をぐるりと散策しながら参拝することをおすすめします。
伝統と新しい風が交差する仲見世通り

雷門を抜けた先に広がる仲見世通りには、江戸時代から続く老舗もあれば、新しい感覚のお店も並んでいます。日本最古の商店街のひとつとされるこの通りは全長約250m。揚げまんじゅうや人形焼きなどの食べ歩き和スイーツに舌鼓を打ちながら散策を楽しむのも一興です。
伝統と新しさが同居する仲見世通り。そこには、時代を超えて多くの人を受け入れて、その時代ごとの文化を見つめてきた浅草寺の懐の深さがにじんでいます。
浅草寺で体感する。季節行事の魅力

浅草寺では、四季を通してさまざまな季節行事が催されており、その度に違った表情で私たちを魅了します。
数ある季節行事のひとつ、「金龍の舞」は、「観音様が黄金の龍として現れ、一晩で千株の松林をつくり、豊かな収穫をもたらした」という、観音様にまつわる伝説に基づいており、1958年に東京大空襲からの浅草寺再建を祝って始まりました。
春と秋の年二回開催され、金龍が境内から仲見世通りを練り歩く姿は、思わず肌が粟立つほどの迫力です。長さ18m、重さ88kgにおよぶ壮大な金龍が音楽に合わせて舞う姿は、さながら本物の金龍が地上に舞い降りたかのよう。音楽に呼応して高鳴る鼓動とともに、目の前を駆け抜けていく姿は必見です。
今日も、明日も〜浅草寺は私たちとともに〜
1400年もの長きに渡り、ずっと浅草のまちを見守る浅草寺。
移りゆくときのなかで変わらずに佇み、「そこにあり続ける」その姿は、浅草の日常に欠かせないものとなっています。時には勝負する勇気を、時には安心感を与えてくれる——浅草寺は、今も昔も人々のこころに寄り添い続けています。
この秋は、浅草、浅草寺界隈の散策でそんな歴史と情緒を肌で感じてみませんか?
ーーー
もっと知りたいあなたに
浅草寺公式サイト
https://www.senso-ji.jp/
仲見世商店街公式サイト
https://www.asakusa-nakamise.jp/
本記事は筆者の見解・体験に基づくものであり、一部一般的な情報や公開資料を参考にしています。

