NY発の新マガジン「RINGO」との出会い〜異なる視点で見つめる文化の未来とは〜
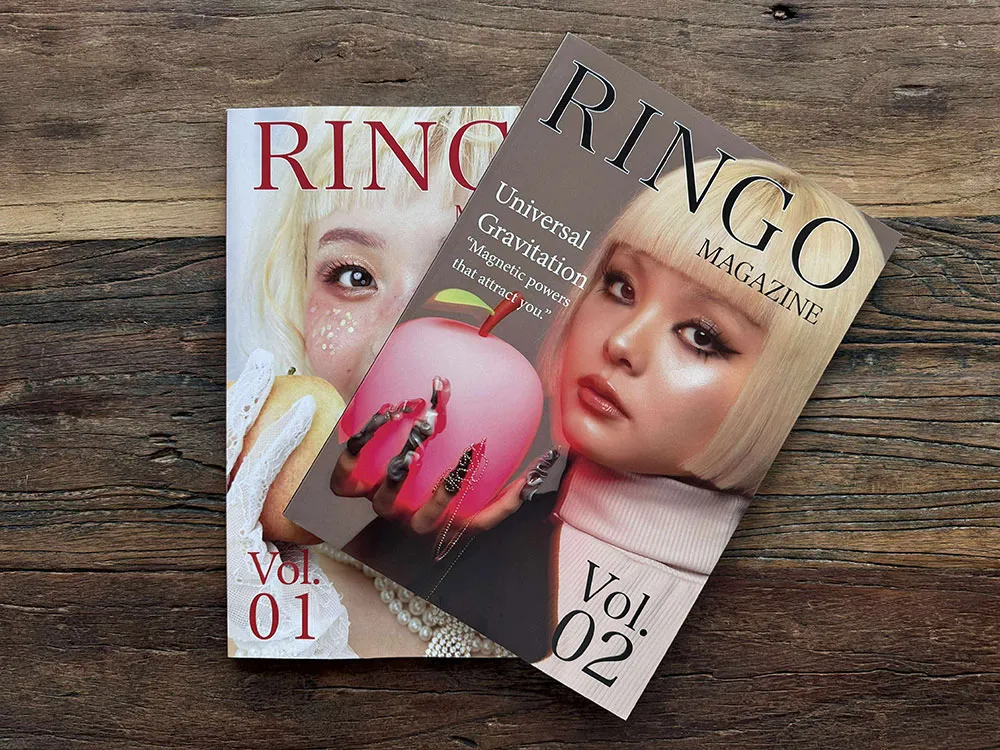
雑誌氷河期と呼ばれる時代に、あえて紙媒体を立ち上げた人がいる。ニューヨーク発の雑誌 RINGO MAGAZINE(リンゴマガジン、以下RINGO)の編集長を務める掛林美紀(かけばやし みき)さん。
創刊は2024年12月。編集スタッフは、世界に点在するパーソンズ美術大学(以下、パーソンズ)の生徒や卒業生で構成されている。パーソンズは美紀さんが編集やデザインを学んだ学校だ。RINGOは、「ファッションとアートをUniversal Languageとし、国境や言語を超えて人々をつなぐメディア」として誕生した。
「子どもの頃から紙の雑誌が好きでした。めくるだけで何度も楽しめる、おもちゃ箱のような雑誌をつくりたかったんです。めくったり、回し読みしたり、積読するだけでなく、好きなページだけスクラップしたり、またそこからコラージュアートを楽しんだり。読者は、読むだけにとどまらず、手にとって自由に使ってもらえたらいいのです。生活の一部に寄り添えるような紙の雑誌を目指していきます」と美紀さん。
情報は容易に、瞬間的に手に入る時代。ウェブ上に溢れる記事は、読み物としての厚みというよりは、軽く文字を追って、情報を頭に入れるものになった。スピード感も情報の重みも異なる。雑誌とは単なる情報の束ではなく、世界をつなぐ「ハブ」であり、「コミュニティ」なのだと改めて気づかされる。
論理の世界から感性の世界へ

美紀さんの歩みはとてもユニークだ。ロンドンで過ごした学生時代、言葉の壁に苦しみながらも、アートや雑誌に支えられた経験がある。それは後に雑誌づくりへとつながる、最初の原体験となった。
帰国後は慶應義塾大学法学部、上智大学法科大学院を経て、外資系コンサル会社に入社。金融機関を相手に、論理の世界で着実にキャリアを積み重ねていった。
しかし2023年、自ら会社を立ち上げると同時に、「足りない知識や技術をきちんと学びたい」という強い好奇心に突き動かされる。翌年には、キャリアの方向性を大きく転換し、仕事の合間の2カ月、ニューヨークのパーソンズ美術大学に短期留学を試みる。そしてそこでの出会いから生まれたのが RINGO MAGAZINE なのだ。
RINGOの編集チームは、東京とニューヨークを拠点に、カナダ、英国、ベルギー、チリなど世界中に暮らすメンバーで構成されている。中心となるのはパーソンズの在校生やアートスクールの卒業生。ファッションやアート、デザイン、カルチャー、ビューティー、クラフト、サステナビリティといった幅広い領域を扱い、週に一度のオンラインミーティングでアイデアを持ち寄る。
そこでは「動ける人が動き、考えられる人が考える」というシンプルなルールが共有され、緩やかなネットワークが新しい編集のかたちを作り上げている。従来の中央集権的な編集部とは異なる、まさに「分散型の編集チーム」だ。

誌名の「RINGO」には、編集チームが出会った街=ニューヨーク(Big Apple)への敬意が込められている。2024年の創刊号ローンチパーティーは、若いクリエイターやアーティストで大いに賑わった。参加者の中には、その場の熱気に触れて「一緒に関わりたい」と声を上げ、そのまま企画に加わる人も現れた。イベントは単なるお披露目の場にとどまらず、コミュニティを広げるきっかけとなったのだ。
やがて、ニューヨークの一部書店でも取り扱いが始まると、偶然手に取った読者から「この雑誌に関わりたい!」というメッセージが届くようになった。雑誌を通じて知らない誰かとつながり、その出会いが次の活動へとつながっていく。小さな縁の積み重ねが、RINGOというコミュニティを有機的に大きくしていった。
最初はニューヨークで始まった活動だが、メンバーの縁によってヨーロッパにも広がった。そこでは、ニューヨークとはまったく異なるファッションやアートの価値観に触れることができたという。雑誌業界が不況だと叫ばれる中でも、「こんなに面白いインディペンデント誌の祭典があるから一緒に出てみない?」と声をかけてくれたのはベルギーの仲間だった。
そうして次の挑戦へと歩みを進めるRINGOは、2025年9月、ヨーロッパ最大のマガジンフェスであるミラノのイベントに参加を予定している。ニューヨークで芽生えた小さな試みが、いまや国境を越えて広がりつつある。その展開は、雑誌が「単なる媒体」ではなく、人と人を結びつけ、新しい文化を紡ぐ「ハブ」となり得ることを証明している。
美紀さんは編集長として、また一人のプレイヤーとして、世界を行き来しながら活動を続けている。雑誌を通じて国境や言語を超え、読者やクリエイターを結びつける——その姿勢は、雑誌を「モノ」ではなく「コミュニティ」として捉えるRINGOの理念を体現している。
KURAFTの挑戦と響き合うもの
KURAFTもまた、独自の挑戦を重ねている。九州大学や和歌山大学と進める産学連携を軸に、学生たちが執筆した記事を誌面に掲載してきた。そこには「ニューロダイバーシティ」という要素もある。心理学を専門とする教授・准教授と連携し、発達障害や精神的な課題を持つ学生が安心して参加できる環境を整えているのだ。職業体験を超え、多様な背景を持つ学生に創造の場を開くことが目的である。
和歌山大学と基本契約締結のお知らせ(https://kuraft.jp/news/905/)
2026年にはグローバル版KURAFTのローンチを予定している。日本の文化を海外に伝えるだけでなく、日本を見つめる海外の人々の視点を受け止めたい。異なる環境や価値観を持つ書き手が関わることで、媒体は必ず深みを増す。単なる多様性の確保ではなく、社会的な意味や存在意義そのものが豊かになっていくのだ。RINGOが描く「コミュニティ」との親和性は、まさにここにあるといえる。
パーソンズの学生、Saraが見た日本
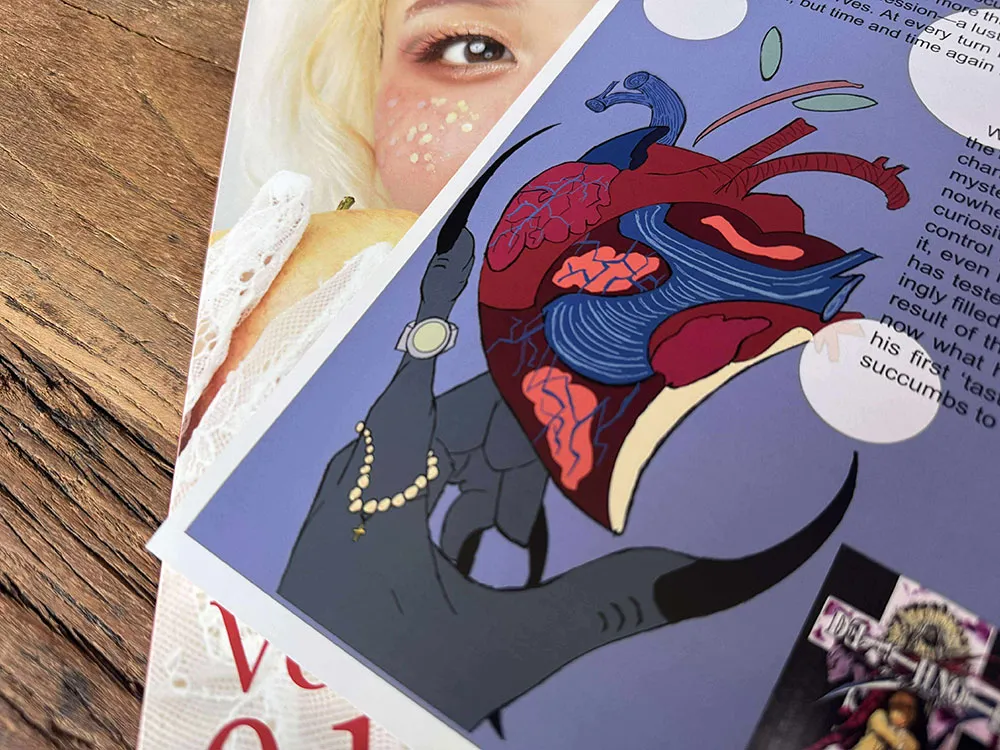
出会いから数カ月後、パーソンズの学生が夏の間の1カ月日本に滞在するという機会に、KURAFT編集部とRINGOチームの交流会を実現した。
編集部を訪ねてくれたのは美紀さんと、イラストレーション専攻の学生Sara。創刊号では、個性ある画風のイラストで誌面に関わっている。
日本の少女漫画「Orange」を愛読してきた彼女にとって、初来日は「憧れを現実に刻み込む時間」だった。神社で御朱印やお守りを受け取り、盆踊りでは小さな子どもからお年寄りまでが輪になり踊る姿に「コミュニティが世代を超えて受け継がれる瞬間」を見た。抹茶の奥深さに感じ入り、駅のホームで整然と並ぶ日本人の姿に驚きを覚える。Saraの目に映った日本は、私たちにとって当たり前の光景の中に文化の本質を浮かび上がらせていた。
雑誌文化の違いと気づき

交流会の話題は自然と「雑誌文化の違い」に及んだ。日本の雑誌は小さな写真を多用し、細部まで丁寧に解説する。一方、海外は大胆なビジュアルで直感に訴える。
Saraは「POPEYEのように特集を軸に多様な要素が一冊に収まるスタイルは新鮮」と語り、「帰国するときには日本の雑誌をたくさん持ち帰りたい」と笑顔を見せた。美紀さんは「KURAFTはフランスで人気のTEMPURAのような海外誌と似た側面はあるが、日本の目線で掘り下げている点がユニーク」と評した。
我々KURAFT編集部も彼女たちとの会話から、意外な側面を発見した。KURAFTがひとつのテーマとして掲げている「地方創生」という概念自体が、米国にはないということだ。日本のような小さな国では、「地元を守りたい」「ふるさとに人を呼び戻す」という価値観が強く、地方創生という言葉が自然に受け入れられている。

しかし、米国のような大きな国では、メガシティー(州)でエリアが構成されており、都市開発や地域再生といった概念はあるものの、「地方を立て直す」よりも「貧困地域の改善」「インフラ投資」「産業誘致」などの個別課題にフォーカスし、その課題も多様なので、なかなか一括りにはいかない。
つまりは、KURAFTが掲げているこのテーマも、グローバル版は、発信目線をよりグローバルに焦点を合わせ、調整することの重要さを再確認した。我々が当たり前だと思っていることが、国を越えると新しい価値になるのだと改めて気づかされた。
紙媒体が生み出すもの

RINGOの誕生は、雑誌というフォーマットがいまだに「新しい物語を紡ぎ出す文化装置」であることを物語っている。デジタルが光の速さで情報の世界(または海)を駆け抜け、瞬間的な熱狂を生むとすれば、紙は手に取り、めくり、残すことで、私たちの記憶に深く浸透していく体験を与える。
ページをめくる動作は儀式であり、そこに印刷された言葉や写真は、何度でも再訪できる「小さな永遠」となる。紙にこだわることは、単なる懐古趣味ではなく、むしろ未来に向けての挑戦なのだ。
KURAFTが試みる産学連携やニューロダイバーシティの探究、そして世界へと広がろうとする挑戦。その歩みの途上で出会ったRINGOは、媒体としての性質も読者層も異なりながら、根底に流れる「文化や思想が交差するハブとなり、人と人をつなげる力」において、確かな共鳴を感じさせてくれる。
では、この先にどんな共同の試みが描けるのか。互いに異質な存在だからこそ、交差点から生まれるものは予測できない。けれども、その「予測できなさ」こそが、未来の物語を豊かに膨らませる可能性の証だ。「一緒に何かをしてみたい」というシンプルな衝動が、やがて思いもよらぬ形で、新しい創造を生み出していくのだろう。
―――
もっと知りたいあなたへ
RINGO MAGAZINE(公式インスタグラム)
https://www.instagram.com/ringo_magazine/

